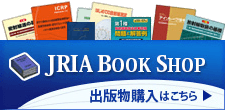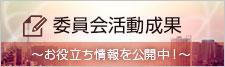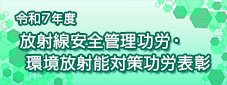| 文字サイズ: |
食品照射の最前線 ~研究者が解説するQ&A~
更新日:2024年5月20日
- 食品照射の最前線 ~研究者が解説するQ&A~ /
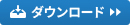 [2.1MB]
[2.1MB]
本書のねらい
本書は、2008年に作成された「食品照射に関するQ&A」(旧ライフサイエンス部会編)を、近年の技術面での発展や国内外の規制や実用化等の状況変化を考慮して、全面改訂したものです。作成にあたっては、商業流通規模の食品・農産物を、安全かつ確実に処理するための照射施設や工程管理についての解説を補強いたしました。また、現在では科学的に解決済とみなされている、旧版にあった安全性試験データへの懸念事項についても、専門家の理解を助けるために、参照出来るように配置しています。
食品照射は、薬剤等を使わない物理的な処理として持続可能な食料供給システムの構築に寄与することが期待されます。わが国の食品安全規制は国際基準とは相違が有り、「食品照射」技術を食品の殺菌や農産物の植物検疫処理に直ちに適用することは出来ません。まずは、技術に対する正しい理解と、社会的な議論が不可欠です。 食品照射について理解して頂くために、少しでも役立てれば幸甚です。
2024年3月
(注1)印刷物等に転載するには、転載許可が必要です。
(注2)委員の所属等は執筆時のものです。
(注2)委員の所属等は執筆時のものです。
目次紹介
| (Q1) | 食品照射のメリットとデメリットは何ですか? |
| (Q2) | 食品照射の国内外での実用化状況は? |
| (Q3) | 食品照射の経済性はどのように考えますか? |
| (Q4) | 照射香辛料の安全性はどのような考え方で担保されていますか? |
| (Q5) | 放射線照射でシクロブタノン類が生成することは、安全性への懸念になりませんか? |
| (Q6) | 食品中のカビのアフラトキシン産生能が照射によって増加することはありますか? |
| (Q7) | 照射食品の表示はどのようになっていますか? |
| (Q8) | 照射食品を検知する技術はありますか? |
| (Q9) | 照射された食品の風味は変化(劣化)しませんか? |
| (Q10) | 食品照射はどのような施設で行われているのですか? |
| (Q11) | 放射線照射施設は、どのような法的規制や管理方法で運営されていますか? |
| (Q12) | 食品照射に関する情報はどこで入手できますか? |
| (Q13) | 過去の懸念について |
| 用語集 |
食品照射の現状と展望
本シリーズは、第2期理工・ライフサイエンス部会食品照射専門委員会が企画し、RADIOISOTOPES誌資料欄(2022年71巻1号~2022年71巻3号)に掲載されたものです。
| タイトル | 執筆者(敬称略) | |
|---|---|---|
| 連載講座 食品照射の現状と展望 今なぜ食品照射か? 連載を始めるにあたって | 等々力 節子 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
|
| (1) | 食品照射とは -技術の概要及び評価と研究開発の歴史- | 等々力 節子 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
| (2) | 食品照射の実用状況と消費者の受容 | 小林 泰彦 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |
| (3) | 放射線照射施設における吸収線量測定 | 清藤 一 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |
| (4) | 植物検疫の仕組みと放射線照射処理の国際基準 | 土肥野 利幸 農林水産省 横浜植物防疫所 |
| (5) | 放射線照射された食品の検知法について | 堤 智昭 国立医薬品食品衛生研究所 |
| (6) | 放射線照射食品の健全性 | 古田 雅一 公立大学法人大阪公立大学 |
| (7) | 低エネルギー電子を利用した新しい食品処理技術の開発 | 片岡 憲昭 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター |
| (8) | 食品照射に関連した新規基礎研究の提案 -食品ロスの削減に向けた損傷菌の制御- | 朝田 良子 公立大学法人大阪公立大学 |
冊子の郵送
上記よりPDFにてダウンロードいただけますが、冊子郵送をご希望の方は、こちらより冊子名および冊数をお知らせください。