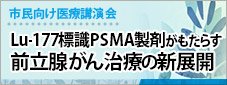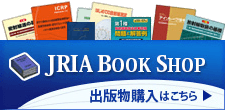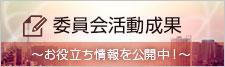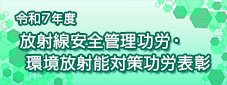| 文字サイズ: |
放射性試薬の安全取扱ガイド2版 Ⅵ
6)汚染の測定
目次
① 概要
② 直接法
③ 間接法(スミア法について)
④ 汚染の評価について
① 概要
・作業台、使用器具、床、手や衣服は放射性試薬で汚染する可能性があります。
・実験の前後と実験中にサーベイメータ等を用いて汚染を測定することで、汚染の拡大を防ぐことができます。
・しかし、サーベイメータですべてのものが測定できるわけではありませんので、測定対象ごとに適した測定器を選択します。
・場所や物の汚染検査は、直接測定する直接法とスミアろ紙等でふき取ったものを測定する間接法があります。
② 直接法
・サーベイメータを用い、物の表面や空間の汚染を測定して汚染を確認します。
| 測定器の種類 | 測定対象 | 概要 |
|
GM管式 (物の表面汚染測定用) |
β、X、γ線 | 一般的なサーベイメータで、通常β線を検出するために使用します。 |
|
シンチレーション式 (線量率測定用) |
X、γ線:NaIサーベイメータ α線:ZnSサーベイメータ 125I:125I用サーベイメータ |
空間の単位時間当たりの放射線量を測定する機器で、ZnS以外は通常γ線を検出するために使用します。 |
(サーベイの方法)
・RIを使用する前(または汚染が確実にない位置)のBG(バックグラウンド)の値を読み取ります。BGの値(GM管式サーベイメータであれば、通常50cpm程度)が異常に高いときには、検出器が汚染している可能性を疑います。放射線安全管理担当者に相談しましょう。
・サーベイメータ―の応答時間(時定数)を短くできる機能があれば、短くします。そして、ゆっくりと測定器を動かし、針が大きく振れる(数値が急増する)場所を探します。
・針が大きく振れる(数値が急増する)場所があれば、その場所で時定数の3倍程度の時間をかけて測定します。
・最も汚染がある位置で保ち、針が安定したところで計数率の値を読み取り汚染を確認します。
③ 間接法(スミア法について)
・スミア法は、⑴そのまま測れない場合(放射性試薬の容器の外側など、そのまま測ると中の試薬が影響してしまうような場合)や、⑵測定対象がα線、β線(3Hや14Cなど、低エネルギーβ線)の場合に選択します。
・専用のろ紙を使い、ざらざらした面で拭き取ります(番号が入っていることが多いです)。
⑴ そのまま測れない場合
・スミア用ろ紙を用いて、汚染が疑われる箇所をまんべんなく拭き取ります。あたりを付けて、一か所ずつスミア用ろ紙を替え行ってください。
・サーベイメータでろ紙を測定します。
⑵ 測定対象がα線、β線の場合
・測定対象はα線、β線の場合は、液体シンチレーションカウンタで測定します。
・低エネルギーβ線(3Hや14C)の核種に特に有効ですが、35S、45Ca、32Pの測定にも用いられることがあります。
(スミアの方法)
・スミア用ろ紙を用いて、汚染が疑われる箇所をまんべんなく拭き取ります。あたりを付けて、一か所ずつスミア用ろ紙を替え行ってください。
・ろ紙の両耳を取り除き,残った円形の部分を液体シンチレータの入ったバイアルへ入れ、攪拌し、液体シンチレ-ションカウンタで測定します。
・得られた計数率から表面汚染密度を求めます。
④ 汚染の評価について
・BG 計数率と有意な差がなければ、汚染なしと判断できます。
・サーベイメータによって評価方法が異なるため、その評価方法について事前に確認してください。